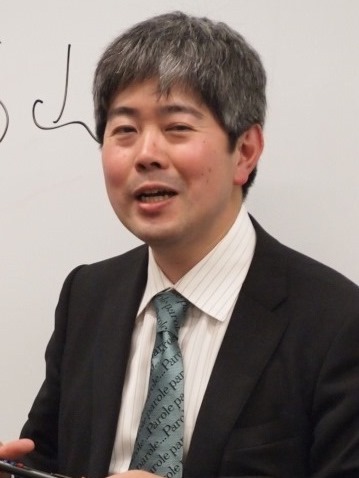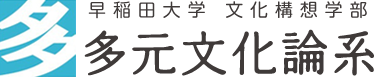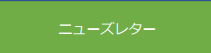教員・スタッフ
伊川健二
- 専門
- 中近世日本と外部世界の関係史
- 担当
- 日本文化史ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
-
この領域では、むかしを相手にしながら、現代的な発想が求められます。中世の日本は東アジアからたまに東南アジアを交流の相手としていましたが、近世になると西はヨーロッパとの関係も生じ、東はアメリカ大陸への移民も散見します。それぞれの相手が多様であれば、関わり方も多様です。日本だけでも、外国だけでも完結しない今日的な複雑さに、みなさんも是非挑んでいただけたらと思います。
井上文則
- 専門
- 古代ローマ史
- 担当
- 地中海文化論ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- 私の研究テーマは、ローマ帝国史です。これまでは特に3世紀の軍人皇帝時代の政治や軍事のことなどを研究してきました。また同じ時代に大流行したミトラス教にも関心をもっています。ローマ史の研究は、学ぶべき語学が多いなど大変な面もありますが、やりがいはあります。関心のある方は、ぜひ挑戦してみてください。
小田島恒志
- 専門
- 現代イギリス小説、現代英米演劇、翻訳論
- 担当
- 異文化受容論ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- もともと「芸術か猥褻か」で裁判沙汰になった『チャタレイ夫人の恋人』で有名なD.H.ロレンスを中心に現代イギリス小説を研究していました。その後、英米の現代演劇を実際に舞台で上演するための翻訳に携わるようになり、「セリフ」を通して英米文化を考えるようになりました。他の関心事はMr.ビーンとイングランド・プレミアリーグ。
垣内景子
- 専門
- 朱子学を中心とした中国近世思想とその日本での展開
- 担当
- 東アジアの生命観と倫理ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- 東アジアに生きる私たちの先人は、かつて西洋由来の新しい思想や学問を、朱子学を中心とする中国思想の言葉を使って翻訳し、必死で受け止めようとしてきました。それらの多くは、今の私たちもそのまま使っています。古い時代の東アジアの思想原理であった朱子学を知ることは、西洋化を経た現代の東アジアに生きる私たちにとって、みずからの思想を見つめ直す大きなきっかけになることでしょう。自分たちのものの考え方や価値観を気付かないところで縛っているものが何なのか、そのことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。朱子学と聞くと、昔の体制教学や古めかしい道徳思想というイメージが強いかもしれませんが、朱子学の最優先課題は人の「心」の問題です。この、いつの時代の誰にとっても無関心ではいられない問題についても、朱子学を通して一緒に考えてみましょう。
- 推薦図書
- ○垣内景子『朱子学入門』(ミネルヴァ書房)○土田健次郎『江戸の朱子学』(東京大学出版会)○丸山真男『日本の思想』(岩波新書)○養老孟司『無思想の発見』(ちくま新書)
河野貴美子
- 専門
- 東アジア文化交流
- 担当
- 漢字・漢文文化ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- 例えば、日本語の文章は今なぜ漢字仮名交じり文で書かれるのでしょうか。このこと1つとってみても、日本の文化を考える上で中国、朝鮮半島への視点は欠かせません。日本文化の諸相をアジアとの関わりの中で捉え直してみましょう。そこから新たな日本のすがたがうかびあがってくるかもしれません。
佐藤尚平
- 専門
- 中東地域研究(アラビア半島現代史・湾岸現代史)、イギリス帝国史研究
- 担当
- 中東・イスラーム文化論ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
-
現在、世界には16億人を超えるイスラーム教徒の方々が住んでいると言われています。2050年までには、イスラーム教徒の人口がキリスト教徒の人口と並ぶという統計もあります。ともに暮らしている人たち、ますます大切になる仲間の世界観を、じっくり学びませんか。

高井詩穂
- 専門
- 日本古典文学、近世芸能、比較文学
Classical Japanese Literature, Early Modern Japanese Theater, Comparative Literature
- 担当
- 国際日本文化論プログラム(JCulP)
Global Studies in Japanese Culture Program (JCulP)
Seminar on Performing Arts Culture in Japan
- 論系進級者へのメッセージ
-
国際化の重要性が謳われて久しいですが、語学を習得すれば真の国際人になれるというわけではありません。日本人が国際的な環境で活躍するには、どんな分野であっても、まずは自国の文化の理解が欠かせないものです。自国の文化を理解することは、他国の文化の尊敬にもつながります。JCulPの授業では、英語を学ぶのではなく、国際的な環境の中、英語で日本文化を学んでいきます。私は特に日本古典文学や古典芸能を担当しています。古典作品には、現代の感覚からはかけ離れた価値観で描かれた作品が多々ありますが、授業では、それぞれの作品を当時の時代背景の中で理解し、それぞれの固定観念や価値観を超越する読解力を培うためのサポートをしたいと思います。その中で、様々なメディアの資料を考慮しながら文学作品等を多角的に分析し、それを英語や日本語で人に正確かつ説得力を持って伝えることができる力、さらに、多様な視点や感覚を受け入れ、自分の視野を広げることができる人材を育てたいと思います。
JCulP offers Japanese students an opportunity to learn about their own culture through an international lens in English, while it offers foreign students an opportunity to learn about Japanese culture in English in a Japanese setting. Through daily discussion and communication with a diverse group of classmates, together we will think about “What is Japan?” and “What is Japanese culture?” from a global perspective, and, at the same time, reflect on our own individual cultures and identities. In my classes, we will read and analyze classical Japanese literature and theater. Japanese culture is probably already foreign for you, and classical Japanese works may feel even more remote. There are many works that are hard to understand from a modern perspective. We will read classical Japanese works in their historical, social, and cultural context, and closely engage with the texts and related materials, going beyond initial impressions and cultural assumptions. I aim to help you improve your critical analysis skills and ability to communicate your ideas persuasively to others, while also broadening your perspective and becoming mindful of diverse points of view.
高屋亜希
- 専門
- 中華文化圏の同時代文化、東アジアの同時代文化交流、20世紀以降の中国現代文学
- 担当
- 現代中国文化論ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- 多種多様なチャンネルを通じ、人やモノがかつてないスピードで国境を超えて行き交う現代にあって、中国の社会・文化も目まぐるしく変化し、例えばアニメや漫画等、日本の同時代文化の様々な断片も、私たちが想像もできない文脈で中国文化に取り込まれています。こうした重層的かつ「多元的」な文化を創造する、進行形の現場に向き合おうと志す、意欲あふれる学生諸君を期待しています。好き嫌いに関わらず、中国はこの先、末永く付き合っていかなければならないパートナーになるでしょう。マスコミ・製造業・建設業・サービス業…どのような進路に進むにせよ、中国の同時代と向き合う体験は、貴重なものになると思います。
- 推薦図書
- 朱大可・張閎 主編、高屋亜希・千田大介 監訳『Chinese Culture Review 中国文化総覧』vol.1~vol.4(好文出版、2005年10月~2007年7月)
・分厚くて、通読するのにものすごく骨が折れる本なのですが、同時代中国の様々な文化的動向を網羅的にキャッチするのに、中国語の資料を含めて、本書を超える本を見たことがありません。

エドワード・チャン
- 専門
- American literature, film, and culture
- 担当
- アメリカ文化論ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- For third-year students, the seminar will be an introduction to American studies, which is an interdisciplinary field of study focused on various aspects of American culture. We will organize our study of America around key topics (many of which are overlapping), such as national identity, race and ethnicity, class, gender, sexual orientation, globalization, immigration, regionalism, foodways, consumerism, countercultures, and so on. Ideally, these will help guide students toward a specific topic for the graduation thesis, for which they will begin doing research during the fall semester. Fourth-year students will conduct research and write their graduation thesis. The seminar will emphasize “active learning,” meaning students are expected to actively contribute to the class through participation, discussion based on homework assignments and presentations, among other things. The course will be conducted entirely in English, and students should be prepared to speak in English during class every week.
中澤達哉
- 専門
- 東欧史 スロヴァキア史 ハプスブルク帝国史
ナショナリズム・スタディーズ
- 担当
- ヨーロッパ文化論ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
-
かつて1990年代の東欧では、ユーゴスラヴィア内戦にみるように民族紛争が多発し、流血の惨事が続いていました。なぜ、東欧の人々は自らの民族や国民のために命を賭してまで戦えるのでしょうか。民族や国民は、いつから、その原理の名のもとに人々を戦争に動員できるほどの政治集団として認識されるようになったのでしょうか。このような問題意識のもとに、 スロヴァキア・ハンガリー・ハプスブルク帝国史を始めとする東欧近世・近代史を研究し、学際的フィールドであるナショナリズム・スタディーズをも専門としています。
これまでの関心は、近代国民が市民権や人権などの近代原理から構築されるだけでなく、それと同程度に中世後期ないしは近世の身分制的・封建制的伝統、特に社団国家原理の援用によって正当化される過程を解明することでした(近代国民法人説)。近年は、こうした伝統的な複合的国制それ自体と、これに規定される人文主義・啓蒙主義・ジャコバン主義・共和主義・普遍帝国概念などの機能と展開とに関心をもっています。また、そうした知識を踏まえ、上記研究と並行的に、現地東欧でのアンケートや聞き取り調査を通じて、EU内での民族的・宗教的マイノリティのアイデンティティの作られ方や変わり方についても検証しています。
東欧は発想の転換の宝庫です。「ヨーロッパのこと」として知っている知識は実は、西欧(あるいはアメリカ!)のものだったりすることがあります。たとえば、歴史上の君主政は「父(あるいは母)→息子」へと世襲で継承されていくものが当然と思っていませんか? 実は、東欧では世襲王政のほうが特殊なのです。ポーランド、ハンガリー、ボヘミアなどは長らく「選挙王政」を採っていました。選挙で大統領を決めるように国王を決める国々なのです。ゼミでは、皆さんの持っている知識をいったん疑ってみることから始めていきましょう。
パウ・ピタルク
- 専門
- 日本近代・現代文学、比較文学、物語論
Modern and Contemporary Japanese Literature, Comparative Literature, Narrative Studies
- 担当
- 国際日本文化論プログラム(JCulP)
Global Studies in Japanese Culture Program (JCulP)
Seminar on Japanese Popular Culture and Media
- 論系進級者へのメッセージ
-
私の授業は議論を中心に行われます。議論を通じ、文学作品をはじめ、あらゆるメディアのテクストを分析する中で、各々の受講生がテクストを掘り下げ、深い洞察を導き出せる場を作りたいと思います。純文学だけでなく、SF、ファンタジー、ミステリーなどのジャンルの文学に興味がある方も、ぜひ参加してみてください!
My courses are discussion-based. I strive to create a space where we can analyze works of literature and other media, and develop our own deep readings together. I am interested in literature of all genres, including science fiction, fantasy and mystery.
タニア・ホサイン
- 専門
- 英語教育学(社会言語学、応用言語学)
- 担当
- 言語・文化・英語教育ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- In my seminar I teach languages and cultures of South Asia, with a special emphasis on Bangladesh, India, and Pakistan. Language has always been controversial issue in South Asia. You will know the role of education in different societies, globalization. This seminar will help you to understand the educational systems, successes, and problems of different countries. It will show how education creates inequalities in the society.

由尾瞳
- 専門
-
日本近代文学、ジェンダー研究、翻訳
Modern Japanese literature, women’s & gender studies, translation
- 担当
-
国際日本文化論プログラム(JCulP)
Global Studies in Japanese Culture Program (JCulP)
Seminar on Diversity in Japanese Culture
- 論系進級者へのメッセージ
-
2017年4月に新設される国際日本文化論プログラム(JCulP)は、日本の学生と外国からの学生が共に、
グローバルな視点と環境の中で学ぶ場を提供するプログラムです。千年を超える長い歴史を持つ日本文学を、グローバルという枠組みの中から勉強すると、
どのような新しい発見があるでしょうか。学生の皆さんには、近代の国民国家形成、グローバリゼーションなどの歴史的背景を踏まえながら、「日本」
とは何か、「日本人」とは何か、「日本文化」とは何か、という根本的な問題を考えてほしいと思います。さらに自分の考え、意見をしっかり持って、
英語で世界に発信することのできる人材を育てたいと思っています。
The Global Studies in Japanese Culture Program (JCulP), to be launched in
April 2017, offers a total immersion global learning experience with a
mixture of Japanese and international students and faculty members. In
JCulP, you will be able to not only study Japan’s literary tradition going
back over 1,000 years, but also explore and access its current vibrant
creative subcultures. By framing Japanese culture from the standpoint of
global and comparative perspectives, we will cultivate global
self-awareness and multiple perspectives that will help you become global
citizens in the new millennium.
吉原浩人
- 専門
- 日本宗教思想史、東アジア文化交流史
- 担当
- 思想文化論ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- 日本を中心に、古代・中世東アジアの宗教と文学・美術・歴史などを研究しています。古典文献を一字一句精確に読解することを目指しますが、同時に作品の生まれた風土を実際に体感することでも、研究を深めていきたいと思っています。

クリストファー・リーブズ
- 専門
- 平安朝漢文学、日本古典文学、比較思想史 = Heian Sinitic letters (kanbun), premodern Japanese literature, comparative intellectual history
- 担当
- 国際日本文化論プログラム = Global Studies in Japanese Culture Program (JCulP)
- 論系進級者へのメッセージ
- My main objective, especially in terms of teaching students, is to explore Japanese culture, literature, and intellectual history (religion and philosophy) within a broader context. To this end, I am forever looking for ways to include within my lectures and seminars material from various East Asian traditions, including China, Korea, and Tibet, as well as from numerous European traditions, both premodern and modern. Hopefully, students come away from my classes with a broader comparative perspective on things. Considering that a great deal of the material examined in class is read by way of English-language translations, I try to have students think with me about the effects of translation on our own understanding. Students who attend my lectures and seminars should expect to read all sorts of things, including poetry, essays, short stories, diaries, plays, academic articles, and more.
渡辺愛子(*運営主任)
- 専門
- イギリス地域研究
- 担当
- イギリス・アイルランド・英連邦諸国(BIC)ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- 多元文化論系に関心があるみなさんは、ある特定の具体的な事象に興味を持っている人が多いかもしれませんが、そういう人こそ、むしろその事象を取り巻くより大きな思想の枠組や歴史的コンテクスト、そしてほかの事象との比較研究などにも積極的に目を向け、大きな視野から考えてみることをお勧めします(もちろん、その多角的研究の素材や方法も、私たちの論系で学ぶことができます)。これにより、もともとの関心領域をよりよく理解できるようになるでしょう。
- 座右の銘(・・・といえるかどうか。。。)
- Healthy Body, Healthy Mind.
- 心に残った一冊
- ・最近読んだ本
平野啓一郎『本の読み方~スロー・リーディングの実践~』
→ 特に日本語スロー・リーダーの私にとって、励みになる本だった。
渡邉義浩
- 専門
- 「古典中国」
- 担当
- 古典中国ゼミ
- 論系進級者へのメッセージ
- 対外的には、三国志の専門家として知られていますが、中国古代(春秋・戦国~唐)を中心に、思想・歴史・文学を学びます。多元文化の特性を生かして、分野にとらわれない広い視座で、さまざまなテーマに挑んでください。
- 推薦図書
- ⚪︎『はじめての三国志 時代の変革者・曹操から読みとく』(筑摩書房、2019年)
⚪︎『漢帝国 400年の興亡(中央公論新社、2019年)
⚪︎『始皇帝 中華統一の思想』(集英社、2019年)
⚪︎『『論語』孔子の言葉はいかにつくられたか(講談社、2021年)
渡邊文佳(助手)
- 専門
- 中東・北アフリカ地域研究、モロッコ史