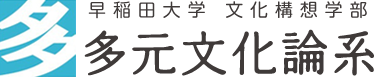「学部時代を振り返って」
文学研究科修士1年 川村卓也
1.ゼミ論文について
私がゼミ論文のテーマに選んだのは、平安時代の漢詩文集『雑言奉和』です。論文では、収録されている全作品に対して逐語的な注釈を施した上で、そのなかで用いられている表現について考察するといった体裁をとりました。なぜそのようなテーマにしたかというと、私は、平安時代、特に嵯峨朝の漢詩文に興味がありました。色々と調べてゆくうちに、嵯峨朝の漢詩文が『雑言奉和』の一部に収録されていることを知り、段々と『雑言奉和』自体に面白味を感じてゆきました。そのような理由で、『雑言奉和』をテーマにしようと決心しました。
ゼミ論文を執筆する上で苦労した点といえば、まず挙げられるのが注釈の部分です。全部で44首の詩と文章1つを含むこの作品に注釈を施すのは、本当に大変でした。図書館で毎日、語釈に用いる用例を探しておりました。また考察の部分では、いかにして先行研究の焼き直しにならないかということについて自分なりに苦労しました。
そのような紆余曲折を経て、論文が何とかできあがった次第です。
2015年3月25日 卒業記念パーティーにて(論系主任の村井誠人先生と)
2.学部時代について
学部時代は、吉原浩人先生のゼミに所属しており、平安時代の漢詩文集『本朝文粋』や『今昔物語集』などといった説話集の輪読に参加しておりました。吉原先生は、本当に厳しく、毎回のゼミでは、担当の発表者は必ず怒られていました。怒られた回数でいうと多分私がトップになるのではないかと思います。しかし、そのようなご指導を賜ったおかげで作品に対してより真剣な態度で臨むことができ、また精神的にも強くなれたのかなと、今となっては感じております。今回、このような賞を頂けたのも、時には厳しい吉原先生のご指導の賜物であると考えております。学部時代に吉原先生に教わって感じたものとしては、「学びは恥をかきながら行うこと」ということです。学部時代、私は色々なことで恥をかきましたが、自分自身のことを客観的に見ることのできない性分の私にとっては、恥をかくという経験は、非常に貴重な経験なのだと、今になって痛感します。大学院に移ったこれからもどんどん恥をかきながら、勉強していきたいと考えております。
また同じゼミでともに切磋琢磨できたゼミ生たちがいたことも自分にとっては、かけがえのない財産です。自分勝手な所がある私が、今まで頑張れたのは、ひとえに、寛容なゼミ生のみなさんのおかげです。本当にありがとうございました。
2015年3月25日 卒業記念パーティーにて(吉原浩人先生と)
3.今後について
私は現在、文学研究科日本語日本文学コースの修士課程で河野貴美子先生の和漢比較文学のゼミに在籍しております。恥をかきながら学ぶ毎日です。修士論文では、学部時代に引き続き、平安時代前期の漢詩文について書きたいと思っております。最後になりましたが、今回、このような伝統のある賞を頂くことができ、推薦してくださった吉原先生や審議に時間を割いてくださった諸先生方には、本当に感謝しております。この場を借りて御礼申し上げます。本当にありがたいことです。しかし自分自身では、あの論文の出来には、あまり納得しておりません。小野梓記念学術賞は、これまで沢山の方々が受賞されてきた伝統のある賞ですが、その歴代の先輩方の論文と比べても、自分の論文には注釈・考察両部分ともに未熟な点が多数あり、「自分などが本当にもらっていいものか」とも感じております。論文での未熟な点は、すべて自分自身の心の弱さによるものです。これからは、自身の未熟な点を虚心坦懐に見つめてゆき、修士論文では、弱い自分と決別したいと思います。「学部の卒業式が人生のピーク」と言われないように、今まで以上に謙虚な気持ちで精進する所存です。