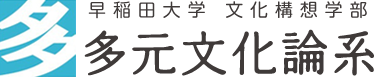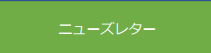現役ゼミ生たちに聞く「○○ゼミってどんなところ?」
異文化受容論ゼミ
梅澤哲彦さん(2015年度 論系進級)
みなさん、初めまして!異文化受容論ゼミ4年の梅澤です。この度はこの場をお借りして異文化受容論ゼミ(以下小田島ゼミ)の紹介をさせていただけたらと思っております。
小田島ゼミでは4年の後期に提出するゼミ論文の提出を最大の目標に、毎週火曜日の5時限目に仲間たちと学んでおります。小田島ゼミの最大の特徴は他のゼミと違って「ゼミ論のテーマに制約がない」点です。したがって、テーマは自分自身の興味関心に委ねられています。先生の専門である英語演劇に関して研究を進める学生がいる一方、「スピードスケート」、「横須賀海軍基地」、「ロックバンド」、「震災報道の変化」などテーマは多岐に渡ります。そうした自分の周りの『異文化』への関心を少人数でディベートし各人のテーマを深掘りし、のちの個人のプレゼンでゼミ生全員から意見をもらい、最終的に論文として自身の考えを文字に起こします。様々な意見が行き交う教室は毎時間とてもエキサイティングです。また、先生のお話は毎回興味深く、考えさせられることが多いです。
加えて、小田島ゼミはゼミ生の仲が良く、ひときわ明るいこともひとつのカラーだと考えています。年に一回あるゼミ合宿では勉強もアクテビティもみんなで楽しみ毎年たくさんの思い出ができます。昨年は伊豆、今年は南魚沼に行きました。また、ゼミ後に行われる懇親会も毎回楽しんでいます。昨年は先生が推薦してくださった演劇を授業終わりに見学にも行ったりしました。
あくまで個人的な意見になりますが、ゼミ選びは残りの大学生活の充実度に大いに影響すると思います。わたしの小田島ゼミでの経験はとても大きな財産となり、かけがえなのない時間となっています。いつでもゼミ見学は承っておりますので、見学に来てください。小田島ゼミで最高の2年間を過ごしませんか!?
現代中国文化論ゼミ
澤田実梨さん(2017年度 論系進級)
当ゼミでは、中国の文化、社会、歴史など様々な角度から中国を学ぶことができます。
3年生が中心となり、課題図書を読み進める中で現代中国の制度や事件、現象に触れるとともに、それらに対する見方を考えていきます。昨年度に引き続き今年度のテーマは“メディア”。中国メディアの体制改革の歴史を学び、実際にどのような報道が行われているのかを事例を見て理解を深めています。中国の記者が中国社会や事件とどう向き合っているのか、日本の報道やイメージとは異なる現代中国の姿に触れることができます。
4年生はゼミ論の完成に向け、研究の進捗状況を発表します。3年次に学んだ議題からテーマを探す人もいれば、全く新しい自身の興味をテーマにする人もいます。現代中国という枠に縛られず、個々の興味を尊重してもらえる点が魅力です。
イ・ダヨンさん(2017年度 論系進級)
現代中国文化論ゼミでは、文化、社会、歴史など様々な角度から現代中国を学ぶことができます。
3年生は課題図書を読み進める作業を通じて現代中国の制度や事件、現象に触れながら、ゼミ生全体で議論し、意見を共有していきます。昨年度(2018年度)のテーマは「メディア」で、20世紀末以降に進められた中国メディアの体制改革の歴史を学び、中国人記者の視点から見た現代中国社会にも触れました。今年度(2019年度)は「横浜華僑社会」というテーマで、19世紀後半に華僑華人たちが横浜に定着するようになった経緯、その後の日本社会の変化と華僑社会の対応などについて学んでいます。今では観光名所となっている横浜中華街がかつてはどのようなものだったのか、どのような過程を経てきたのか。課題図書を読み進め、お互いに疑問や意見を出しあい、理解を深めています。
4年生はゼミ論の完成に向け、研究の進捗状況を発表します。3年次にゼミ授業を通じて学んだ内容からテーマを探す人もいれば、全く新しい自身の興味をテーマにする人もいます。現代中国という枠に縛られず、個々の興味を尊重してもらえる点が魅力です。
現代中国文化論ゼミは中国語が話せなくても、中国に関する知識があまりなくても大丈夫です!非常に長い歴史を持っている中国に関して幅広く勉強できるゼミなので、きっと楽しいと思います!
思想文化論ゼミ
佐藤由季さん(2015年度 論系進級)
思想文化論ゼミを一言で表すならば、「メリハリのあるゼミ」だと思います。ゼミとしては、3年生は『本朝文粋』、4年生は『今昔物語集』の一部の作品に、注釈をつけ、典拠を探し、現代語訳するという内容です。図書館に通い詰めて資料集めをし、膨大な時間を本や論文と向き合って過ごしますが、適切な図書の探し方をマスターでき、今となってはゼミ論文を書き上げるために、とても有り難いと感じています。実際、苦労して作り上げた資料はきちんと評価してくださり、また何が足りなかったのか、どのようにすればよかったのかも指摘してくださるので、達成感も一入です。
各学期の終わりには、ゼミ生全員での打ち上げコンパがあり、年2回の合宿でも交流を深めています。全員参加の夏合宿では、1泊2日でゼミ論構想発表や史跡参観、任意参加の海外研修では、台湾や中国などに4~5日ほど行き、先生の解説付きで現地の史跡や博物館などを参観できます。ゼミ生は歴史好きばかりなので、この時ばかりは勉強を忘れてのびのびと楽しんでいます。
このゼミの専門は、漢文や東洋思想・文化などですが、まるで別ジャンルの論文を書かれる方もいます。もちろん、そういった方々にも先生は対応してくださり、細かなアドバイスをいただけるので、ゼミ選びに困っている方でも大歓迎です。ぜひ一度ゼミ見学にいらしてください!皆様にお会いできることを楽しみにしています。
漢字・漢文文化ゼミ
藤井悠平さん(2015年度 論系進級)
漢字・漢文文化ゼミでは日本を含む東アジア地域共通の文化基盤になっている「漢字・漢文文化」について、その特質や問題点などを様々な角度から考察します。 ゼミの進め方としては文献を事前に読んできて、自分が興味や関心をもった個所についての発表をおこないます。 ゼミ生自らが意欲的に考え、使用する資料や発表方法を工夫して演習形式での授業を展開していきます。 学生による主体的なゼミ運営によって学問的な知識だけでなく、知識のアウトプットの方法も学びます。ゼミ担当教授の河野貴美子先生は海外を飛び回っているパワフルな先生です。 ゼミの時間が始まる前には集まって先生の興味深い海外の土産話を聞くのが一つの習慣となっています。学生の発表に対しては鋭い指摘をすると同時に、豊富な経験から新たな見識を教えていだたけることが多く、発表を準備して臨んだ学生よりも詳しい、といったことが頻繁に起こります。 教授と学生、それぞれの様々な視点から見解や考察が飛び出し、議論が起こる楽しいゼミです。
東アジアの生命観と倫理ゼミ
西山風紗さん(2015年度 論系進級)
こんにちは!私たちは「東アジアの生命観と倫理ゼミ」です。難しそうなゼミ名ですよね。この名前には、どのような意味が込められているのか。…それはここでは語り切れないのでひとまず、私たちがどんなことをしているのか、紹介いたします。
まずはゼミの進め方について。構成は
第一部:共通文献(教科書)の読解
第二部:各人の研究の進捗発表
といったもの。要は毎週、「代表者が読解・研究内容を発表→議論」を繰り返し行っているということです。
今年度扱っている文献は、森三樹三郎著『上古より漢代に至る性命観の展開:人性論と運命観の歴史』。私たちは東アジアの思想を中心に勉強していますので、それに関する優れた論文を選んで読んでいます。ゼミ員から扱う文献を提案することもできます。難文も皆で読めば怖くない!
先ほどゼミのテーマについて少し触れましたが、卒論で扱えるテーマの幅は広いです。江戸の思想家から西洋思想との比較まで、あらゆる文化を扱えるのはさすが多元文化論系のゼミだなと思います。
また、毎年夏に自由参加の合宿が行われています。行先は香港・台湾・中国など、希望者で話し合って決めています。引率の先生も付きますので、安心して参加できます。
思想・哲学・宗教・歴史に興味のある皆さん。研究テーマから上下関係まで…?とても制約の少ない私たちのゼミで、一緒に学びませんか。お待ちしています。
地中海文化論ゼミ
惣田琢巳さん(2015年度 論系進級)
はじめまして!地中海文化論ゼミの惣田です。本ゼミについて進め方や雰囲気、研究テーマ等に触れながら紹介をしていきたいと思います。
・「地中海文化」とは?
本ゼミにおける「地中海文化」の定義は特にありません。自分がこれは地中海文化だろうと感じたならば、それについてやればいいのです。井上先生はテーマ設定にはあまり口出しはせず、どうしたらもっと深められるかというアドバイスをしてくれます。そのため、ゼミ生は自由にテーマを設定することができます。
・ゼミの進め方・雰囲気
ゼミの進め方はゼミ論文の作成という最終目標に向けて、学期に1度の発表とディスカッションを通してステップアップしていくスタイルです。3年生に求められることはゼミ論文のテーマ設定です。研究テーマが既にある場合はそれを、とはいえ、まだ決まっていない人の方が多いので興味のあること(今後テーマは変えても良い)について発表し、4年生の発表を聞いたり、ディスカッションを通して模索していきます。4年生は研究テーマを深め、ゼミ論文の作成をします。
ゼミの雰囲気はゆったりとした印象です。先生もゆったりとした方でとてもアットホームです。体育会、サークル、バイトに従事する者と色々なゼミ生がいて、このような多種多様な学生が所属しているコミュニティーというのは学問以外でも様々な学びがあるなと個人的には感じています。今年の3年生は女の子が多くゼミに華やかさが生まれ、飲み会なども行っています。ゼミ合宿では伊豆に行ってきます。楽しみですねぇ~。
・ゼミ生の研究テーマの紹介
4年生
ヴェルサイユ宮殿の建築様式がもたらす影響
現代地中海におけるギリシャ神話
ローマ帝国の滅亡
オットー・ワグナーから見る建築様式の変遷
スペインの黒い伝説はなぜ持続したのか など
3年生
ヴェネツィアのモーゼ計画
ローマ五賢帝時代
ヨーロッパの城の形成 など
最後に
先にも触れた通り、ゼミは学問はもちろんのこと、多くのことを学べる場であると思います。色々なゼミがあり迷ってしまうかもしれませんが、学生生活を彩る自分に合ったゼミを探してみてください。それが地中海文化論ゼミであったらうれしいです。
中東・イスラーム文化論ゼミ
木村俊輔さん(2015年度 論系進級)
大学1、2年生のみなさん、初めまして。中東・イスラーム文化ゼミにて昨年幹事長を務めました木村と申します。今後やってくる論系進級やゼミ選択という、大きな選択の前に、私の所属するゼミのことを知っていただき、少しでも興味を持っていただければ幸いです。
中東・イスラーム文化ゼミでは、中東地域全般、イスラームに関することを幅広く扱います。「イスラーム」というと、皆さん中東の果てしない砂漠をイメージされるかもしれません。(実は私もその一人でした)たしかに、発祥は中東地域です。しかしながら、現在イスラーム教徒人口の最も多い国は、実は東南アジアに位置するインドネシアなのです。
このように、イスラームは世界的に見てかなりの人口を有する、非常にグローバルな宗教です。イスラームと聞くと、規律の厳格な宗教で、どの地域でも画一的な文化・生活様式を持っているとイメージしてしまいがちですが、国によってもその在り様は千差万別です。これほど広範囲に世界中の地域を扱うことのできるゼミは珍しいかもしれません。そういった点もまた、当ゼミの魅力と言えるでしょう。
近年、政情不安やテロ事件などから、イスラームや中東諸国について、否定的なイメージを抱いてしまう人は少なくありません。イスラームは日本にとって、まだまだ身近なものとは言えません。そうであればこそ、先駆者として、学問的な取り組みや、直接に触れあう機会を通じて、真摯に理解しようとする姿勢を持ち続けることが必要なはずです。当ゼミにはある意味、時代の負託ともいうべき、大きな使命が課せられているともいえるでしょう。
さて、少しかたいことを書いてしまいましたが、やはり気になるのはゼミの雰囲気だと思います。当ゼミには、好奇心旺盛で活発な、行動力のある学生が多数集まっています。ゼミの活動中も、オープンに意見を言い合うことができ、学年間の壁もありません。毎年、多くの学生が海外留学や、海外旅行へと旅立っていきます。そのようにして得た類まれな経験などを、中東料理を囲みながら語り合うというのもまた当ゼミの醍醐味です。
多種多様な学生の集まる当ゼミは、知識の有無を問わず多くの人に門戸を開いています。私自身、不肖ながら幹事長を務めさせていただいたわけですが、実は予備知識も少ないままこのゼミに入りました。(恥ずかしながら、イランではアラビア語を話していると思っていた私が、今ではイランについて卒論を書いています)イスラームや中東を学びたいという想いが少しでもあるなら、当ゼミをぜひ、選択肢に加えてみてください。
大学4年間のうちの半分を過ごすことになるゼミです。ここで築いた人間関係は、きっと生涯の財産となるでしょう。どうか、皆さんにとって生涯の友に出会えるようなゼミを見つけられることを祈念しています。そしてそれが、中東・イスラーム文化ゼミであれば、とてもうれしく思います。
ユーラシア文化論ゼミ
田中晴子さん(2015年度 論系進級)
ユーラシア文化論ゼミの田中です。
これからゼミ、もしくは論系を選択する1,2年生に向けてゼミ紹介をしたいと思います。
まずユーラシア文化論ゼミは、個人が自由に興味を持ったテーマについて取り組んでいます。また (3年生は特に)ゼミに入ってすぐに一つのテーマに絞る必要もありません。私も3年生の時はロシアの前衛美術について取り組んでいましたが、4年生になって日本の伝統工芸品にガラリとテーマを変えました(笑)
このゼミで大切にしていることは(ゼミ要項に書いてある通り)自分の興味をもったこと(もの)について、いかに相手にも興味を持ってもらえるように発表できるかどうかです。これは社会人になってからも必要となってくる能力だと思います。私も班内で発表し、聞いてくれる他の人の反応を見て、「自分が伝えたいことに関心を持ってもらえたかどうか」を勉強させてもらっています。当然興味を持っていることは人それぞれなので全員に関心を持ってもらうことは簡単なことではありません。しかし、関心を持ってもらえた時とそうでない時の差は質疑応答の意見を出す姿勢から見て違います。
自分の興味を持ったことをとことん掘り下げて研究したい人も、それを周りに伝えたいと思っている人にも、このゼミは役に立つと思います!以上です。
小澤奈那さん(2015年度 論系進級)
ユーラシア文化論ゼミの小澤です。ゼミの内容や特徴を紹介します。
ユーラシア文化論ゼミは1学年15人いるため、5つのグループに分かれ、毎回1人が班内に向けて発表をする形で進みます。それに加えて3年生は春学期に1度、全体に向けての発表をします。また、夏休みには伊豆高原のペンションで合宿、冬休みにはゼミ論執筆缶詰め合宿(こちらは非公式)を行います。
このゼミの魅力は、とにかく自由にテーマ設定ができるところです。担当教員である源先生は、どんなテーマに対しても真摯に耳を傾けてくださいます。例えば今年の4年生は、軍事郵便、妖怪、聖書、ゆるキャラ、ソシュール、ホラー映画などに取り組んでいます。過去には家系ラーメンでゼミ論文を書いた人もいたそうです。テーマ設定の仕方も多様で、最初から一貫して同じことをやり続ける人も、色々なことをやりながら徐々に絞っていく人もいます。私自身は日本中世史をテーマにしていますが(先生曰く、日本もユーラシア大陸のうち)、他の分野からの意見を聴くことで、思いもよらない発見をすることがよくあります。
様々な関心を持った人が集まり、お互いの意見に耳を傾けあうという意味で、最も多元文化論系らしいゼミです。「異文化交流」の場に身を置きたいという方には、ユーラシア文化論ゼミをおすすめします。
西辻亜以子さん(2014年度 論系進級)
ユーラシア文化論ゼミの卒業生であり、現在大学院でも、源先生に指導教員としてお世話になっている西辻亜以子です。
ユーラシア文化論ゼミは、源先生の深い教養と愛情に助けられながら、「ユーラシア」という範囲をもはや超越した、さまざまな国や地域の中から、ありとあらゆるテーマを研究できるゼミです。先生のご専門はロシア文学、比較文学、書誌学などですが、それ以外の分野に関しても幅広い知識をお持ちです。
自らの研究テーマを決め、論文を書き進める時、研究対象の似通った人たちが集まるコミュニティの中で、専門的な意見を交換しながら進めていくことはもちろん重要なことだと思います。ですが、まったく関係のない分野の人と話し合うことによって、急に気づくものがあったり、思わぬ発見や、解決の糸口が見つかったりすることが本当にあるものです。
先生もよくおっしゃっていることですが、ゼミ発表では「その専門分野ではない人にわかりやすく伝えること」がとても重要です。レジュメをしっかり整えること、専門書から引用した文章のみで伝えるのではなく、しっかりとその意味を理解し、考え、自分の言葉で説明することによって、見えてくるものが必ずあります。
個性豊かすぎる学生が常に集まってくるので、とても刺激的な(?)ゼミです。迷っている方は是非一度ご検討ください。
ヨーロッパ文化論ゼミ
新藤綾佳さん(2018年度 論系進級)
大学1・2年生の皆さん、はじめまして。ヨーロッパ文化論ゼミの新藤です。
これを読んでいるということは、どの論系に進むか、どのゼミに入るかを考えていることかと思います。そんな皆さんに多元の「ヨーロッパ文化論ゼミ」について簡単に紹介したいと思います!
<ヨーロッパ文化論ゼミとは…?>
本当に簡単に紹介すると多元の中で一番新しいゼミです!私は2020年に大学4年生になりましたが、私たちの代がゼミで3期目です。ゼミとしての暦は浅いですが、2019年には多元の中でゼミ希望者が一番多いなど実力・人気を備えたゼミです。
ではゼミの中では何をしているのか。ゼミは毎週火曜日の3限(2020年現在)にあり、春は地域・国別に分かれて学習、発表を行います。昨年はドイツ、フランス、東欧、美術、スポーツなどのサブゼミに分かれて学びました。このサブゼミはその時のゼミ生の興味によって作られます。そして秋は4年生はゼミ論文、3年生はゼミ論文への準備を行います。各自が発表を行い、お互いにフィードバックなどを行います。ゼミの内容としては以上です。
<ゼミ生たちはどんなことに興味があるの?>
ゼミの先生である中澤先生の専門は東欧のスロヴァキアやナショナリズムがですが、ゼミ生が興味のあることはかなり幅広いです。
例えば昨年では、ヒトラーやフランス王朝、現代ポピュリズムに関することからファッション比較研究、お笑い、に関する幅広いテーマでゼミ論文が書かれました。このように時代においても古い時代から現代まで、ジャンルにおいても歴史からファッション、芸術、スポーツなど多岐に渡ります。
<最後に>
その分野に興味があり、学びたいという気持ちがあればかなり柔軟にどんなジャンルも学べるゼミだと個人的に思っています。中澤先生は文キャンで講義も行なっているので、少しでも興味の湧いた方は是非一度受けてみるのもいいかもしれません。皆さんにお会いできることを楽しみにしています!
イギリス・アイルランド・英連邦諸国(BIC)ゼミ
福岡修さん(2015年度 論系進級)
イギリスアイルランド英連邦諸国ゼミ(BICゼミ)は「知的に楽しい」をモットーに学習するゼミだ、とかつて渡辺先生は仰いました。僕たちゼミ生はこう思いました。〈知的に?〉僕は聞き間違いかと思いました。でも確かに先生は「知的に」と仰ったようで、それは周りのゼミ生のひるんだ顔を見て確信に変わりました。
多元文化論系は、文化構想学部随一の多様性を持つ論系です。中でもBICゼミの懐の広さは群を抜いていて、ひるんだ顔をしていた彼らや歴代の先輩方は本当に素晴らしい発想力の持ち主達です。そんな彼らは、日々ゼミにおいて切磋琢磨し、お互いを高め合っています。
あるゼミ生はこう言いました、「マサイ族に会いに行ってきた」。なんでも、失恋で悉く摩耗してしまった彼の心は、マサイ族と一か月衣食住を共にすることでしか回復できなかったそうです。僕は〈馬鹿かよ〉と思いました。次に、〈なんでマサイ族なんだよ〉と思いました。
しかし、実はこの「なんで?」がとても大事なのです。そして一見難解で理解がかなわなそうな事象でも、「そもそもどういうことなのか」という根源的な疑問を持ち、答えを見つけ出そうとする姿勢。これこそが「学ぼうとする」ということなのです。最後に疑問に見合う答えに辿り着いた時に感じる快感や喜びは計り知れないものです。
〈これが「知的に楽しい」ということなのか〉と、〈これがBICゼミの真髄なのか〉と、入ゼミ早々思い知らされました。BICゼミは、学ぶことや知ることを果敢に楽しむ上品なゼミです。ぜひ、ゼミ選択で迷っている2年生はその選択肢にBICゼミを入れることを一考してみてください。ここでは素晴らしいゼミ生活があなたを待っています。
終わりに、僕は例の彼に何故マサイ族なのかを聞きました。彼は「なんとなく」と言いました。僕は〈やっぱり馬鹿かよ〉って思いました。
アメリカ文化論ゼミ
髙橋みのりさん(2016年度 論系進級)
アメリカ文化論ゼミでは、春学期はアメリカ映画をテーマに研究しました。具体的には、アメリカ映画の代表であるディズニーや西部劇などを、実際の作品の鑑賞を通して互いの意見や感想を英語で発信し合いました。また、研究し考察する土台として、映画研究のアプローチ方法や様々な視点について書かれた英語の文献を読みこみました。先生曰く学期や年で扱うテーマが変わるらしいので、映画以外の事も研究すると思います!
少人数のゼミなので、毎回1人1人が活発に自らの意見を発する機会に恵まれています。また、チャン先生は1人1人にしっかり向き合ってくれるので、勉強意欲もますます強まります。また、大衆文化として長く親しまれている映画について、今まで持っていなかった視点からアプローチすることで、アメリカ映画と日本映画の繋がりや影響、優れた映画の撮影技術や編集技術について研究することができ、物語の面白さという物差し以外の様々な物差しを得ることが出来ました。
ゼミのメンバーの中には、高い英語力を持つ人もいれば、これから自らの英語力を伸ばしたいという強い意思を持っている人もいるので、英語力で言えば互いに切磋琢磨できる素晴らしい環境だと思います。その上、優しいチャン先生のもと個性豊かな明るいメンバーが揃っているので、楽しいゼミ授業を受けることが出来るかと思います。
陳佳欣さん(2016年度 論系進級)
One of the most attractive things about this seminar is that you will learn various aspects of American culture. There will be a discussion between professor and all students. We will discuss about the culture background and the history as well. This seminar is also a platform to practice and improve English skills since all the written and oral work is required in English. Those who want to study American culture will all find what you want in this seminar.
言語・文化・英語教育ゼミ
尾崎友里恵さん(2016年度 論系進級)
はじめまして!大まかにいうと当ゼミでは、言語について学ぶことができます。
前期は、主に日本での英語教育について学びます。皆さんは、小学生もしくは中学生のころから英語を学んできていると思います。どのような方法で英語を教わりましたか?それらは役に立ちましたか?日本の英語教育の問題とはどのようなものでしょうか。それらをいくつかの記事を読みながら時にはディスカッションを交えつつ考察していきます。
後期は外国の言語に着目します。日本の公用語は日本語で、(方言はあるにしろ)ほとんどの日本人が日本語を話します。しかし、外国に目を向けるとどうでしょう。公用語がいくつもある国があり、同じ国民でも全く異なった言語を話す国がたくさんあります。一度も植民地化されたことのない日本においてはあまり馴染みありませんが、多くの国の言語は植民地化されたその国の歴史や、地形などの影響を大きく受けています。いかにしてその国の言語が今日の地位を確立し保ってきたか、今後その言語はどのように変化していくかなどを、言語政策や教育、国民のアイデンティティ、グローバル化など様々な側面から考察していきます。
ゼミはとても少人数でアットホームな雰囲気です。先生もとても優しく、ひとりひとりに目を向けた指導をしてくださいます。
授業は全て英語ですが、事前課題に取り組めばあまり心配要らないと思います!
卒論のテーマも制限がなくそれぞれ関心のあるテーマで研究することができるので、少しでも興味があれば言語・文化・英語教育ゼミを考えてみてください~!!
You can study about all about language education in this seminar.
In the spring, we study about English language education in Japan. We see the present situation of English education and discuss about possible improvements to the system, and more effective ways to learn English.
In the fall seminar, we focus on other countries. For example, this year we are looking at former British colonies - South Africa, Jamaica and Ireland. You can learn about language, education and culture from every aspect.
Our seminar has a few students so it is a tight-knit group and that is why we all getting along well. Each student focuses on the countries and policies they are most interested in. You can study whatever you want. We are looking forward to seeing you!
日本文化史ゼミ
出相智之さん(2018年度 論系進級)
日本文化史ゼミ
当ゼミでは、海外文化を取り扱うゼミが多い多元文化論系の中でも日本文化・日本史をメインに研究を行っています。3年次は津田左右吉『文学に現はれたる我が国民思想の研究』や日本史史料の発表を通じて歴史学への理解を深め、4年次は各自が関心を寄せるテーマに沿って討論や個別指導を通じてゼミ論文の完成を目指します。テーマも「斎宮」「春画」「官僚制度」「文字」「漫画」「妖怪」「武士道」「百貨店」「城」など任意で設定できるため、多岐に渡ります。また、6限には有志でくずし字や和製漢文の読解を勉強する機会もあります。
また、築地市場見学や歌舞伎鑑賞、大相撲観戦などの文化に関するイベント活動や、学外の関係者による講演も随時行っています。9月にはゼミ合宿を開き、参加任意ながら多くのゼミ生に集まっていただきました。日本史に興味がある方もこれから勉強されたい方も、是非お待ちしています!
伊川健二先生
伊川先生もゼミ同様2017年から早稲田大学にいらっしゃった先生です。1年生から受講出来るオムニバス形式講義「日本史・世界史再発見」や英語「Intensive Studies12」、多元論系演習など色々な授業を受け持っています。伊川先生のゆるふわっとした雰囲気を見てみたい方はこれらの授業も参考にしてください。
Seminar on Diversity in Japanese Culture
野澤玲奈さん(2019年度 論系進級)
はじめまして!JCulP4年 「Diversity in Japanese Culture」ゼミの野澤です。由尾先生にこのような機会をいただいたので、存分に大好きなゼミについて語ろうと思います。4年間あるJCulP生活の中でも2年次までは、毎日同期やJCulPの先生に会っていると思いますが、3年次以降は全体で会う時間もほとんど無くなります。その中で、ゼミは大学の集大成です。誰とどんなテーマで締めくくりたいかを慎重に検討していただきたいと個人的に思っています。
「Diversity in Japanese Culture」ゼミは、その名の通り、多様性に溢れています。卒論テーマも、文学、映画、教育、マーケティング、SNS、歌舞伎など多岐に渡ります。先生の底知れぬあたたかさの中で、ゼミ生が自ら自由に興味関心を深めています。ゼミは、自分のテーマを 共有し、話し合いの中で、 一見異なるテーマ同士の中でジェンダーやアイデンティティ、ナショナリズム、歴史など共通する概念を見出し、深堀します。また、由尾ゼミの醍醐味は先生の招くゲスト講義です。ゼミ生のテーマの最前線で研究をされている方を授業に招き、新たな視点を加えてくれます。
最後にゼミの個性についてお話しします。由尾ゼミの学生は「真面目な自由人」ばかりです。自らの世界観の中で、お互いを尊重し、それを学業に活かせる人が多いと思います。各年、学生の雰囲気は変化するとは思いますが、自主性を保ちつつ、人として向き合ってくれる、母親のようなあたたかさの先生の元で、ゼミ生はのびのびと育てると思います。最後まで自分の興味関心と向き合いたい方とゼミでお会いできることを楽しみにしております。
JeongHoon Leeさん(2019年度 論系進級)
In Professor Yoshio’s zemi, Seminar on Diversity in Japanese Culture, we challenge the myth of Japan as a homogeneous country by analyzing multiple aspects of Japanese culture and society under the umbrella terms of diversity. With the key themes of diversity, gender, globalization, and multiculturalism, the zemi mainly focuses on class discussions on particular topics and readings, and also sharing and offering helpful feedback to other members about our research progress. Class discussions and interaction with other members is the foundation of the zemi. We are very open and considerate about sharing our personal experiences and opinions and listening to others, so it is a stimulating learning environment where we can learn from each other.
Our research topics are also diverse, and range from literature, theater, media, family culture, linguistics, and education. My own research is on representations of Zainichi Koreans in contemporary Japanese film. Through the connections of Professor Yoshio, we also have great opportunities to meet students and scholars from other universities, who provide us with helpful pieces of advice on our research, as well as their insights on specific current issues related to diversity and Japanese culture. Some of the issues we discuss are very difficult and complex, but they are vital issues that are relevant to today and that do not have simple answers or solutions.
University is a place where there is space to openly discuss important issues such as diversity and gender, and about our own identities to change society for the better. I believe that there is none other like this zemi environment where we can freely discuss and share our opinions; a space that I feel comfortable in learning and sharing ideas. I hope to cherish this opportunity and connections with my classmates even after I graduate Waseda.