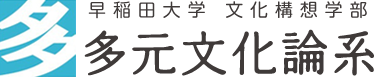この授業・ゼミ・先生が面白い!
第2回 現役ゼミ生に聞く―思想文化論ゼミ編
思想文化論ゼミ4年の田中です。今回は、どのゼミに行こうか迷っている多元文化論系の皆さん、またこれから論系進級をしようとしている皆さんに、私の所属する思想文化論ゼミの紹介をしたいと思います。 思想文化論ゼミは、皆で特定の作品を精読し、それぞれが発表する形式で進みます。昨年度は、平安時代の漢詩文学『本朝文粋』の詩序に註釈を施しました。語句や表現の典拠を探すために図書館に通うことになりますが、自分で調べる訓練になり、色々な場面で役立ちます。 本年度前期は、『今昔物語集』の巻二十七を読み、自らの関心に引き寄せて発表しました。この巻二十七には鬼や狐が登場する怪異譚が多く収録されて おり、ゼミ生がそれぞれの切り口で「物語をどう読むか」を考えました。ゼミの課題をこなすのは非常に大変ですが、ゼミ生同士の情報交換も活発で、どの代も 仲が良いです。 また、夏期休暇中にはゼミ合宿をおこなっています。昨年は河口湖・甲府に行き、浅間神社や甲斐善光寺を見学しました。今年は箱根の大雄山や石仏群、箱根神社を見学しました。 本ゼミではゼミ合宿に加えて、年に一度、希望者による海外への研修旅行を行っています。昨年は台湾に行き、故宮博物院や台湾大学を見学しました。もちろん、九份や夜市などでの観光も楽しむことができました。この研修旅行は任意参加ですが、個人的には是非参加することをお勧めします。先生や他のゼミ生と共に異文化に触れることは、必ずや皆さんにとって良い思い出になると思います。 これらの活動と並行して、三年生からゼミ論文の準備をします。ゼミ生の関心は多岐にわたっており、現四年生は以下のようなテーマで書くことを予定しています。
- 天狗
- 唯識説
- 巨大ロボットと巨人伝説
- 『江島縁起』
- 河伯の受容
ゼミの先生の守備範囲が広いので、このように各々が自由にテーマを設定しています。常時ゼミ見学も受けいれていますので、東アジア・日本の思想に興味がある方は、是非見学しに来てください。 ゼミの紹介で終わってしまいましたが、以上、【この授業・ゼミ・先生が面白い】でした。
第1回 現役ゼミ生に聞く 漢字・漢文文化ゼミ編
みなさん、初めまして。漢字・漢文文化ゼミの須田健三郎です。
これから後輩として多元文化論系に入る方や、既に入っている方の科目登録の参考にしていただければ、幸いです。
では、さっそく紹介していきたいと思います。
まずは、後輩に向けて「情報発信」という意味も兼ねて、ゼミ紹介をしたいと思います。
「漢字・漢文文化ゼミA」
ゼミの進み方は文献を読んできて、自分の興味や関心に寄せて発表します。ちなみに、昨年読んだ文献は「和漢朗詠集」「蒙求」などで、発表時間は1人40 分程です。また、自分の卒論のテーマ設定やその途中経過を発表する機会もあります。入ってみて、予想に反して堅苦しい雰囲気がないです。同期は、私を含め 7名で、非常に仲がいいと思います。そして何より、自分たちで主体的にゼミを運営していける環境です。担当教員である河野貴美子先生は早稲田大学OGで、 バレー部出身です。
論系合宿後、ゼミで軽井沢を散策した際には、先生の体のどこにそんなパワーがあるのかわからないくらい歩きました。ですので、後輩の為にアドバイスをすると、私のゼミは非常に楽しいですが、歩く際には体力もいります。
次に私が受講した「演習」で特に印象に残っているものを簡単に紹介したいと思います。
「英語圏の言語政策」
この演習は発表がなく、どちらかというと講義に近いです。内容は海外や日本の言語政策です。例えば「公用語と標準語の違い」など、言語に興味があれば非常に楽しいです。
「漢字文化」
この演習はオススメです。なぜかというと先生が期末試験の際にお茶を用意してくれたからです。 授業内容は甲骨文字や字書・義書・韻書など。
「詩・歌の可能性」
この演習も楽しかったです。水谷八谷先生が代行していたのですが、洋楽に詳しい人や米国の歴史を知りたい方にはオススメです。音楽を聴きますが、その歴史を知ってから聴くのとで全然違う印象を受けることにビックリしました。
「英語圏フィクション」
月曜日の1限で起きるのは大変でした。しかし授業内容は翻訳が中心で、正解がない分大学生らしい授業。
主観的になりましたが、以上、私の【この授業・ゼミ・先生が面白い】でした。