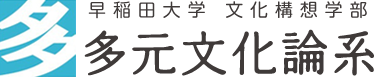ゼミ・卒研
2016年度ゼミ論文・卒業研究タイトル一覧
異文化受容論ゼミ
- 東京の町並み景観の成り立ちと、その向上に向けて~欧州都市から学ぶ~
- 日英皇室・王室比較から考える日本人と天皇の距離
- イギリスにおける紅茶の普及
- 1990年代における日本ストリートファッションの変化
- 日本人の英語力の実態と各段階の学校教育における英語教育の問題点の考察
- 日本人の国民性
- 若者の音楽行動~ライブキッズの例から~
- 幸福度の高い社会を構築するノルウェー社会の実態
- 和太鼓文化における伝統性と革新性
- 宮崎駿論:『風たちぬ』を通して
- 翻訳から見る固定観念―ハリー・ポッターにおける役割語について―
- 麹の役割と今後の日本での役割について
- 現代日本における広告文化
- 観光産業における日本のおもてなし考察~ディズニーから倣う~
現代中国文化論ゼミ
- タバコから見る各時代別中国社会―日中比較を中心に
アジア近世史ゼミ
- 『文明の衝突』に対する反論と脅威均衡理論の再検討─日米同盟を軸に─
- サリット首相とプーミポン国王にみる政府と王制の関係について
- 尖閣諸島における事業を中心とした古賀辰四郎の生涯と、その領有権問題への影響
- 清朝初期における杭州の駐防八旗について
- 満蒙独立運動と満州国建国─皇帝擁立から見る性質の違い─
- アヘン戦争期における清朝の西洋認識と禁書
日本文化論ゼミ
- 銀座の街並み―その変遷についての推察―
- 徳川吉宗の流鏑馬復活に関する研究
- 演劇とサブカルチャー
- 当世具足の特徴が変遷する要因について―肥後細川家当主の当世具足の変遷―
- 『平家物語』における重衡説話成立に関する研究
- 織田信長の御茶湯御政道、その定義と目的について
- 南方熊楠と「一大理体」
- 近代ヤクザに関する肯定的考察
- 明治時代における手妻文化衰退の真相
思想文化論ゼミ
- 坂口安吾作品にみる陶酔世界―酩酊と堕落の関連性―
- 笑わないアリスのイメージと作品の関係
- 『南総里見八犬伝』と動物妖怪譚―化け猫の妖怪と狸の混同―
- サルドゥ『ラ・トスカ』の西洋と東洋―オペラ『トスカ』と落語『名人競』の邂逅の可能性―
漢字・漢文文化ゼミ
- 明清楽の受容と変容
- 『源氏物語』の装束描写と物語
- 琉球の文字文化―「文字らしきもの」の使用背景―
- 人名表記にみる古代日本の漢字の受容
- 描かれた新撰組~虚構と真実の姿を探る~
- 日記文学にみる異文化との接触
- 江戸時代の社寺参詣―伊勢参り大ブームの理由とは―
- 元代における章草流行の要因について
- 日本と漢字、日本の漢字
- 『義経記』に描かれる義経像
- 現代韓国人の漢字認識
- 日本における〈ひじり〉概念の変遷
- 「桃花源記并詩」と「桃源行」をよむ
東アジアの生命観と倫理ゼミ
- 善会・善堂に見る「善」の意識
- 劉一明研究
- 朱熹の鬼神論について
- 神仙道流派の受容における倫理的要素とその意義
- 本居宣長「もののあはれ」の思想について
地中海文化論ゼミ
- ジェイン・オースティン『自負と偏見』の限嗣相続
- ユリウス・カエサルの視野、思想
- フランスにおける移民問題解決の糸口―ローマ人とフランク族の事例を参考に
- ルネサンス期ヨーロッパでは、なぜギリシャ・ローマの神々が芸術の世界に数多く登場したのか
- ローマ庶民の生活とローマ文明の発展
- ギリシャ経済危機の原因究明
- ヴェネチア共和国とその根底にあるもの
- 18世紀スペインにおける国民国家の形成
- 元首政期の古代ローマ帝国における軍隊の経済活動への影響について
- ローマ帝国の滅亡とキリスト教の関係
- ローマ帝国と元朝の比較から見る、多民族国家ローマの長命の理由
中東・イスラーム文化論ゼミ
- エジプトカイロの地下鉄建設の歴史と概況
- ビルマナショナリズムと国内の宗教民族問題の多面性―歴史的背景と根本敬論を踏まえて―
- 中東現代美術展開催と多文化主義
- 詩と社会―アフマドフアードニグムから見るナーセルの時代―
- 日本の公教育におけるイスラーム
- ポールボウルズにおける他者表象の模索―『蜘蛛の家』における主人公に着目して―
ユーラシア文化論ゼミ
- 柴幸男『わが星』におけるモノローグ表現についての考察
- 沖縄とハワイの神話、民話の比較~ポリネシアという源流~
- 現代ロシアにおけるナショナル・アイデンティティの模索―ロシア正教と軍事に依拠する国家―
- ルーツ・ミュージックとしてのアイルランド音楽
- 声楽における理想的な高音発声方法
- なぜ今敏は「鬼才」とよばれたのか―今敏の鳴らした警鐘―
- アイドルブームのメカニズムについて―私はなぜアイドルに〝ハマる〟のか―
- 集合住宅をめぐる話
- 映像制作実習 1年間の軌跡
- フリードリヒ大王の思想と戦争~『反マキアヴェッリ論』とシュレージエン戦争再検証
- ビデオゲームが持ちうる悪影響と、それを取り巻く社会の在り方
- 日本におけるキリスト教受容 遠藤周作『沈黙』をめぐって
- 日本における西洋音楽の受容 唱歌教育の導入と発展
- シャネルNo.5はなぜ伝説になり得たのか
ヨーロッパ近現代文化論ゼミ
- アメリカとメキシコの国境
- 活版印刷術がもたらすイギリスの子ども観―〝子ども誕生″の意義とは―
- ズデーテン地方の変遷
- イタリア・オーストリア国境における「国境ゼロ化」~言語と国境の不一致より~
- 移民問題から見るイタリア論―イタリア全土に現れる‘自己中心主義’―
- ジプシーとハンセン病患者から見る差別構造
- フランスに見る移民問題―移民と共生するためには―
- ボスニア内戦発端最大の要因―ボスニア共和国内外における諸問題の考察―
- 現地語の地名の日本語表記に関する考察~流動する日本語訳~
- 武士道と騎士道の比較及び合気道の立ち位置
- ルクセンブルク大公国 近代国家成立と国民意識の形成
- フィンランドの教育から得る教育の理想
- ハンガリーの「民族」統合―難民割り当てに対する国民投票の背景―
イギリス・アイルランド・英連邦諸国ゼミ
- イギリス国内の対ヨーロッパ政治の中にみるBrexit
- 「硫黄島プロジェクト」二部作に見る戦争映画の意義
- イギリスにおける移民、及び「移民問題」の論拠の計数的検証
- 日本カジノ誕生に伴って懸念される社会問題とその解決策 ~ギャンブル依存症犯罪組織マネーロンダリングの観点から~
- イギリスにおける階級制度とパブ~その歴史の変容と国民生活への影響~
- イギリスは国内のムスリムとどのように共存していくべきか~衣食における文化の衝突から共存の可能性を探る~
- イギリスが国際政治で果たしているグローバルな役割を考える~イギリス外交政策とその目的の変遷を考察して~
- 創造都市における歴史的建造物の意義~横浜BankART1929とリバプールMetalのアートスペースを通して~
- 日英の働く女性の姿~育児と仕事の両立から見える課題~
- ハニフォード事件から見るイギリスの多文化主義報道
- もうひとつの〝Winnie the Pooh〟~ディズニー版プーが原作にもたらした変化~
- Jリーグとプレミアリーグの比較から読む日英のサッカービジネス発展
- 日本におけるハーフ(mixed)の人々のアイデンティティのゆくえ
- 現代イギリスにおけるキリスト教~多文化社会の中での宗教の将来~
- ビートルズの曲からみる戦後社会のアイデンティティ形成~集団と個の関係性~
- 英国におけるコーヒーハウスの発展と日本の喫茶店文化のこれから~英国のコーヒーハウス文化とジャーナリズムの観点から~
- ナショナルトラストから見るイギリスのナショナリズム
- サッチャリズムの「英国病」への効能~精神的アプローチの観点から~
- 階級を超えてイギリス人の国民的飲料になった紅茶~女性が紅茶の普及において果たした役割~
言語・文化・英語教育ゼミ
- English Language Education Policy for immigrants in Australia ―The case study of Japanese immigrants—
- English Education in High School in Japan—A Case Study of One Advanced High School in Kanagawa Prefecture—
- The Comparative Study of English Language Education between Indonesia and Japan
アメリカ文化論ゼミ
- Free Schools in the U.S.A. with a Focus on the Background in the 1960s
卒業研究
- 手遊び「せっさん」考―「せっさん」の語源とは何か―
- クルマの大衆化とその歴史―国民車とはなにか―
- 古着に見るファッションのこれから
- 世界に触れるということ:『アメリ』に於ける身体的接触と視覚的接触による知覚
- モンドリアン その生涯と芸術
- プロ麻雀団体の実態調査
- 東京の墓地文化の形成とそのゆくえ―民主化された死の再興への考察―
- 高橋源一郎『虹の彼方に』における「全世界」性の分析―「詩のリズム」・「半音階法」から「メロディー」を探す―
- 日本の奨学金制度はいかにあるべきか
- 千利休
- 社会における犯罪小説の存在意義